�R�t�i��p�����͔�̍쐬���@����т��̃|�C���g���Љ�܂��B
�ǎ��͔̑���쐬�ɓ����āA���L��3�_���|�C���g�ƂȂ�܂��B
1�D����
�����̎�ނ͏o���邾�������̎�ނ̗L�@���𑽂��܂ނƁA���ꂼ��ɉ����Ĕ��������������A�P���Ȕ������p�łȂ��A����ނ̔������p�����܂�܂��B���͔̑�𓊓����邱�Ƃɂ��A�y��̔������p�����l�ɂȂ�܂��B
2�D�Y�f��
�Y�f���i�b�^�m��j�������Ȃ�ƕ����ɂ����鎞�Ԃ������Ȃ�܂��B�܂��A�P���ɂb�^�m�����łȂ��A���O�j���E�Z�����[�X�E�w�~�Z�����[�X�̊����ɂ�蕪�x�ɕω����N����܂��B�ڍׂɂ��Ắu�L�@���̒Y�f���v���Q�Ɖ������B
3�D���x
�͔���쐬����ɂ������āA�K�����x��60���ȏ�ɂȂ�悤�ɁA�����E�����E���𐮂��Ă��������B�͔�̍쐬�Ə̂��āA���x���グ���A���������̏ꍇ���L��܂��B���̏ꍇ�A�a���ۂ��c��A�G���������邱�Ƃ��L��܂��B�܂��n�x���オ�炸�A�U�z�����ېA���ɊQ��^���鋰�ꂪ�łĂ��܂��B
�͔�̍쐬�̍ہA���x���オ�炸�A���������̏ꍇ���L��܂��B���̏ꍇ�A�a���ۂ��c��A�G���������邱�Ƃ��L��܂��B�܂��n�x���オ�炸�A�U�z�����ېA���ɊQ��^���鋰�ꂪ�łĂ��܂��B
�͔�Ɋւ��鎑��
1�D�L�@���̒Y�f��
2�D��ʓI�ȑ͔�̍���
3�D���~�K���͔�̍쐬���@
4�D���O�j�����𑽂��܂ޑ͔�i�o�[�N�E�����������j�̑���������@
5�D�����̃R�t�i�̏����ɂ���
�Y�f���ׂ������ł́A���x�͂킩��܂���B
���x�́A�Y�f�@�ے��̃Z�����[�X�E���O�j���̊����ɂ���ĕω����܂��B
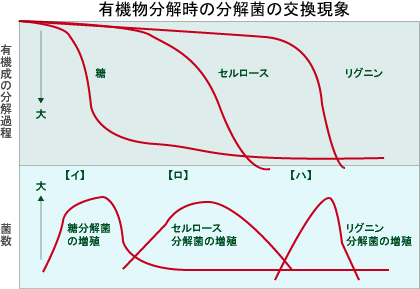
�L�@�����ނ̗L�@�����g��(�������聓)
| T-C | T-N | O/N | �g�f���v�� | �Z�����[�X | ���O���� | �g�^���p�N | |
| �p�[�N���� | 37.6 | 1.950 | 19.3 | 4.9 | 12.2 | 36.7 | 12.2 |
| ������� | 39.1 | 0.650 | 60.2 | 25.0 | 37.0 | 11.2 | 4.1 |
| ���~�K�� | 40.1 | 0.541 | 74.1 | 16.3 | 41.9 | 20.6 | 3.4 |
| �������� | 42.2 | 0.334 | 126.0 | 21.5 | 48.2 | 15.5 | 2.1 |
| �������� | 50.4 | 0.208 | 242.0 | 10.9 | 48.2 | 30.5 | 1.3 |
| �������� | 40.6 | 0.290 | 140.0 | 6.8 | 55.2 | 15.3 | 1.8 |
T-C:�S�Y�f�@T-N:�S���f�@C/N:�Y�f��
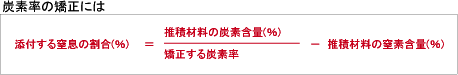
�͔�Â���̃|�C���g�͈ȉ���3�_�ł��B
2�D�Y�f���F������~�K��������A�{�����������Ă����y�͒x���Ȃ�܂��B
3�D���@�x�F�Ȃ�ׂ��������Ȃ�H�v���K�v�ł��B
���ۂɂ�
�E�ΊD���f�p���Ȃ��ʼn������B
�E MIC-108����������Ƃ��͌����S�̂ɂȂ�ׂ��ψ�ɍ�����悤�Ɋh�ق��܂��B
�E MIC-108������̓r�j�[�����Ŕ핢���܂��i�����A���x�̕ێ��j�B
�E ��Ԃ��͔��y������1�`2��s������A���̌�͐�Ԃ��Ȃ��ʼn������B
�iMIC-108�͌��C���ێ�̂ł��̂ŋ�C�̂Ȃ����S�����甭�y���܂��B�j
�E �͐ς���R�͑傫���A�������܂��i���x���オ��Ղ��Ȃ�܂��j�B
�E MIC-108���g�p�̏ꍇ��1�`2�d��1�܂��ڈ��ł��B�{����̂̏ꍇ�ƃo�[�N�₨�������������ꍇ�͑��߂Ɏg�p���ĉ������B
�E �L�@���̓����\�����Ȃ���o���邾������ȗL�@�������ĉ������B
MIC-108���g�����Ƃɂ��
�E �͔쉻�������Ȃ�܂��B
�E �͔�̌����Ɋ܂܂��a���ۂ�Z���`���E�ُ̈푝�B��}���܂��B
�E �͔�̌����Ɋ܂܂��L�@����_�앨���z���Ղ��h�{�ɂ��Ă���܂��B
�����x��60���ȏ�ɏオ��悤�ɂ��ĉ������I
�G���̎�E�a���ۂ�}���A�͐ώ��Ԃ�Z������ׂɂ͉��x��60���ȏ�ɂ���K�v���L��܂��B
�E ���������������ďオ��Ȃ��ꍇ�A�r�j�[���̔핢���͂����A��Ԃ����������ĉ������B
�E �������s�����Ă����x�͏オ��܂���B����Ȃ��ꍇ�́A�����������ĉ������B
�E ��𐫑@�ہi�o�[�N�E�����������j���������x���オ��Ȃ��ꍇ�A�Ăʂ����̈Օ��𐫂̂��̂��[���ĉ������B
�����䌧����s�͔̑�쐬��ł��B
�ޗ��F�_���ō쐬���Ă��镲�Ӗ��k�ɔA�f�������Ă�����̂��݂����1�`2t�ɂ��uMIC�|�P�O�W�v�i���e��10�����j���P�g�p
�Ăʂ�����1�`2t�ɂ�100�������a

�o���邾�������ς݁A������50�`60%���x�ɒ������܂��B
���̌�r�j�[���Ŕ핢���܂��B���̌�2���������ɝ��a���܂��B
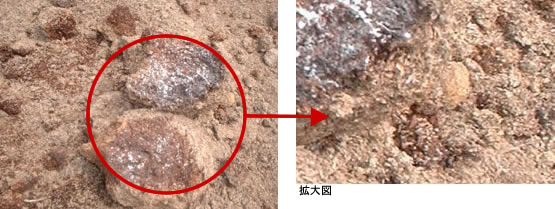
11�����{�ɑ͐ς��A6���̏B�����܂Ŕ������ɂ�镪�����i�݂܂��B
���~�K�����ꕔ�`���c��̂�����܂����قڕ���܂��B
�����ł́A�p�ۏ����g�����͔�̐�����@����܂��B
���p�ۏ��͔쐧����@
�i1�j�������a�@ �i�p�ۏ��E�Ăʂ��E�r�[�����i���f���Ƃ��āj�j
�i2�j��������
�i3�j���x��60�`70���ɂȂ�A���̌㉷�x��������n�߂�ΐ������������a
�i4�j���a���s������A���x��45�����z���Ȃ���Δ��y�I��
�i5�j�͐�
�i6�j���R�������A�����ʂ�30���ȉ��ɂȂ�Ί���
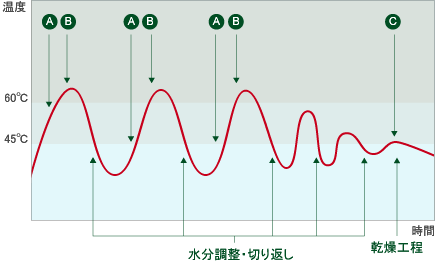
�i�`�j��������
����A�~�m�_�Ȃǂ̈Օ��𐫕������D�C�I�ɕ�������A����̑�������ۂ�D�C�ۂ���Ƃ��Ċ������A�ċz�M�ɂ���Ĕ��M���N����܂��B����ۂ͂S�O�����Ɛ������ł��Ȃ��Ȃ�A���͍������x�ɋ��������ۂȂǂ����B���܂��B
�i�a�j�@�ە�����
�����ۂ͎���ۂ������ł��Ȃ������@�ۂ����܂��B���̎����͉��x��60���ȏ�ɂȂ�A�����ۂ������܂��B�������D�C���̕����ۂɂ���Ăփ~�Z�����[�X�����A�Z�����[�X���ނ������ɂ��܂��B���̂Ƃ��_�f��ɏ���邽�ߎ��͂��_�f�s���ƂȂ�A�����Ɍ��C���̃Z�����[�X�����ۂ̓����܂��B���̂悤�ɂ��čD�C���ۂƌ��C���ۂ̖������S�����藧���A�@�ێ��̕������i�݂܂��B���̂��߉��x�������蕪�����ɖ��ɂȂ�ƕ����𑣐i����ׂɍēx�_�f��⋋����K�v���L��A��Ԃ����s���܂��B
�i�b�j���O�j��������
�����ۂ̐H�ׂ�G�T�����Ȃ��Ȃ�Ɖ��x���������Ɖ������Ă��܂��B����ƕ����ۂɂ���ĕ�������ē�炩���Ȃ����@�ۑg�D��H�ׂ邢�낢��ȍۂ������Ă��܂��B���̂��납�烊�O�j���̕������n�܂�܂��B���̎����͑@�ې����̒��ԕ�������A���x���ቺ���đ��̔��������ɐB���܂��B
1�D�ǂ��q������邽�߂�
�i1�j�q���̒��f������p�i���f���g���ŏI�I�Ƀ^���p�N������܂��B�j
���D�Ɏ_�Ԓ��f�ŋz�����đ̓��ŃA�����j�A�ԂɊҌ�����A����ɗt�ō��ꂽ�Y���������������āA�A�~�m�_���o�ă^���p�N�ƂȂ�܂��B
���D�A�����j�A�Ԓ��f�ŋz�����A�t��苟�������Y�������ƁA�������Ŕ������ăA�~�m�_�ƂȂ�A�n�㕔�Ɉڍs���ă^���p�N�ƂȂ�܂��B
�i2�j�y��������̃A�~�m�_�����Ɩq���ւ̋���
�������͗L�@�������ăA�~�m�_�����A���ɒ��ڋ�������B
2�D���n���_�n�тł̖��
���n�����𑽓�����ƁA�Օ���L�@���ʂ��ߏ�ƂȂ�A�y���ŏɎ_�����ۂ������ƂȂ�Ɏ_���ߏ�z������܂��B����ɋC�ۏ�������Y�������̐��Y���}�����A�A�~�m�_����^���o�N�������j�Q����A���̌��ʖq���̓��ɏɎ_�����܂�܂��B
3�D�R�t�i�ɂ�鋍���̉��P����
�R�t�i�ɂ��A�\�߈Օ���L�@�������ĕ��A�������܂��B
�܂��A�������ɂ��A�~�m�_�������s���A���ƕs���ł��^���p�N�������������܂��B
4�D�R�t�i�g�p���@
�i1�j�o���N���[�i�[�Ŕ��o���ɁA�͔�1�g���ɑ��R�t�i�P���i���j15������1�܂�Y�����ĉ������B���A�������ɂ͒��[�e�P�{�p�ɂ���w���ʂ�����܂��B
�i2�j�͐ό�̐�Ԃ��́A���y�M�������肩�������_�Ő����������܂߂�1����x��Ԃ��ĉ������B
�i3�j�R�t�i�g�p�̊��n�����͔�̑��n�{�p�ŗǎ��q�����o���܂��B


